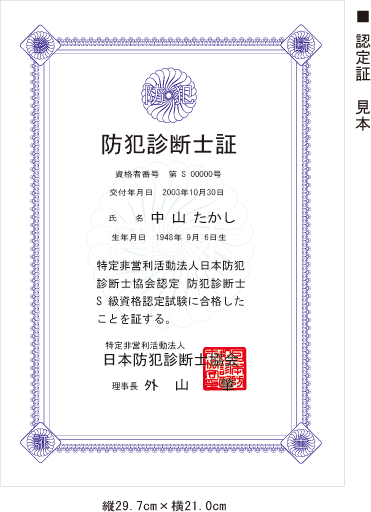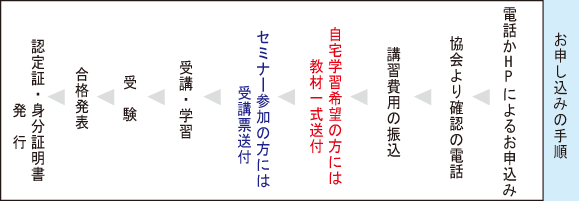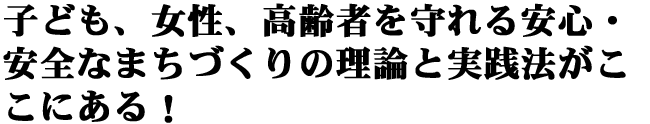
|
子ども、女性、高齢者、住宅やマンション,
安全・安心まちづくりなど
守りたいもののリスクを軽減する
総合防犯のスペシャリスト養成講座
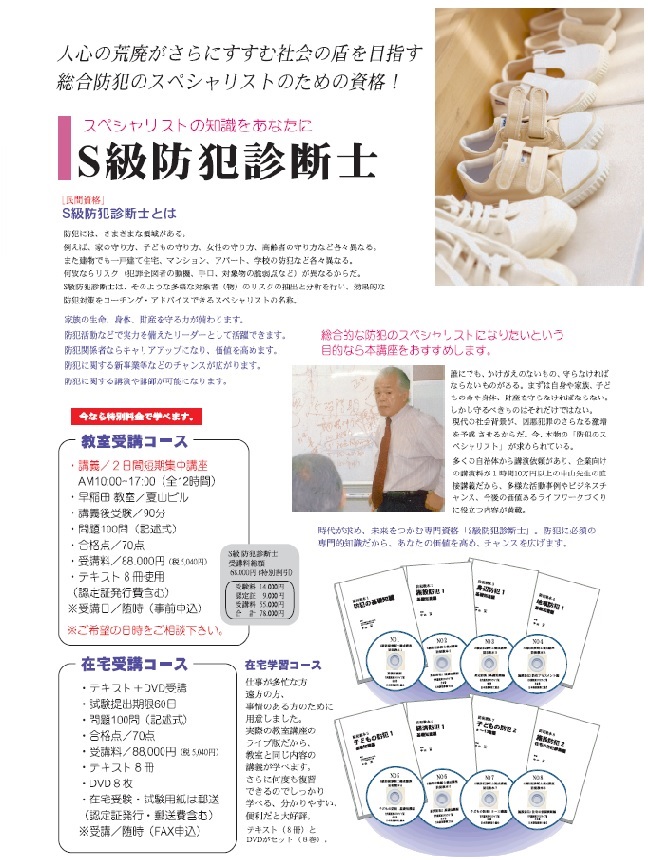
|
|
愛知県豊田市による「安心・安全なまちづくり活動」はたいへん優れている。多くの人々は、予算がたっぷりある自治体だからなどと考えている。だが、豊田市の「安全なまちづくり」の最大の特長は、「安全まちづくり条例」を実施するための「防犯活動行動計画書」(アクションプログラム)を作成し、毎年、検証・評価して改善していることだ。
安全なまち作り活動に限らず、どのような組織でも、活動でも一定期間を経たら検証し評価し改善しなければならない。そのような基本的なことすら行なっていない自治体や関係者は少なくない。自主防犯活動グループの崇高な活動を有効にしなければならない。安全なまちに近づけなければならない。それが計画・立案する関係者の責務である。
間違っても、活動グループの方々の理由にしてはならない。!安全なまちにするためには多くの専門的な知識が不可欠である。尊い住民の皆様の活動を無駄にしないために多くのことを知ってもらいたいものだ。
■市民講座のプログラム・下段参照
■子育てと子どもの守り方講座のプログラム・下段参照
|
|
|
|
国分寺市の「市民のための防犯出前講座」を終えて
市民の皆様と市の取り組む姿勢に感銘しました。
|
平成20年11月29日から5回に及んだ「市民のための出前防犯講座」が終了した。中部、東部、北部、西部、南部地区ごとに「各公民館」で行いました。市民の中には、同じ内容にもかかわらず何度も受講される方々がおられ、驚きました。今回は、防犯とは何か、といった本当に基本的な内容だったのですが、とても感動しました。また、市の担当者の方がたも「防犯」に関する専門知識をしっかり取得されており、打ち合わせでも共通言語が使えとても助かりました。 9月から「防犯リーダー養成講座」がはじまりますが、今から、とても楽しみにしています。 お金儲けでもない、また、権力目的でもない、ただただ、純粋に「自分の住む町を守ろう、自分の住む町の子どもたちを守ろう」という崇高な精神をもたれた市民の顔は光り輝いています。そのような方々にお会いできるのが、この仕事の冥利です。。
■市民のための防犯出前講座の内容
○防犯とは
・防犯の基本
・防犯の定義
2つのリスク
・防犯理論
|
○地域防犯3つの力
安全なまちづくりの具体的要点
5つの活動
防犯リーダ−
活動メンバー
・住民
・行政
・自治体 |
○地域特性・犯罪動向
必須のテーマ住民力
街頭犯罪の軽減
・侵入盗対策
・非侵入盗対策
・人身被害対策 |
○被害回避の法則
・事前回避力
・危険対応力
・危機脱出力 |
○具体的防犯活動
・テーマの選定
・ルール化
・優先順位
・目的と目標
・協力者
・予算と保障
ほか |
|
|
|
| 平成19年度にいくつかの市町村を対象に「犯罪のないまちづくり仕掛け人養成講座」の開催を計画さ れているようである。県が中心となって、積極的な姿勢で住民の方々の尊い活動を支援すれば、今後数年のあいだに、他の市町村のモデルとなる安全なまち・地域が出現する可能性はきわめて高い。 |
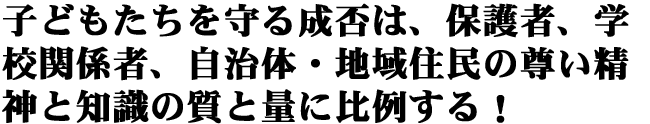 |
|
子どもたちを守れる家庭・地域づくり
子どもたちを守る効果的な知識と指導法!
|
平成18年10月20日、熊本にある学校法人の主催で「迫りくる犯罪から守るための保護者の
防犯セミナー」を行なった。保護者に限らず市の関係者、婦人団体、各種活動グループの指導者
などを含め多数参加いただいた。講演終了後、参加者の方から「もっと詳しく」などとの要望が
よせられている。この時の講演内容を参考までに公開しておく。
■迫りくる犯罪から子どもを守るために
保護者のための防犯セミナー
■第一話 迫りくる犯罪から子どもを守る前に
○今のままでは子どもたちを守れない!
○その6つの理由
○現代の防犯の死角と盲点
○防犯の定義と基本と理論
■第二話 子どもの防犯の基本
○子どもの何を、誰が、どう守るのか
○どこで、どう守るのか
○子どもを守るための防犯の基本知識
○子どもを守るための12のテーマ
○子どもの防犯3・6・4の法則
○子どもを狙う犯罪者
○保護者が気をつけること
■第三話 子どもの防犯 具体的指導法
○9歳が基礎指導年齢の目安(3つの防犯力)
○6つの指導領域(場面)と4つの指導の要点
|
○登下校時に被害を受けないためのキーワード
「誘う手口」「車を使う手口」「突然、襲う手口」
「正目的・被害」
「危険察知力・危険対応力・危機脱出力」
○学校内でダメージや被害を受けないために
「いじめ」「わいせつ・セクハラ被害」
○公園や路上などで遊んでいる時の指導法
「必須、8つの誘いのパターン」
○建物の内外で被害を受けないために
「最も危ない環境だが‥」
○自宅に一人でいる時に
○携帯電話やインターネット使用上の注意
■第四話 保護者の防犯、必須知識
○保護者の油断と隙という盲点
○保護者の防犯の基本、侵入者抑止
○自宅は危ない空間、安全な空間にする
○自分や家族の生命・身体を守るために
|
|
|
|
| 今、いじめ問題で世間が騒然としている。いじめはやめさせられるのか、できるのか、できないのか
など議論百出である。だが防犯の専門家からみれば、小学生のいじめは100%近くやめさせられる。中高校生のいじめのほとんどもやめさせられる。やめさせられないのは文科省、教育委員会、学校関係者、保護者らが真剣に取り組んでいないからである。さらに加えておけば、現場の学校関係者の責任は
少ない。責任の大半は学校を管理監督・指導する責任のある人々であり保護者なのだ‥。 |
|
子どもたちを守る防犯理論がここにある
自治体・教育関係者、保護者から大反響!
|
子どもを被害者にしないための新理論!
子どもの防犯には12のテーマがある。
| 年齢別指導 |
保護者 |
学校関係者 |
自治体・ボランティア |
| 1、6歳になったら4つの約束/保護年齢 |
1 |
2 |
3 |
| 2、9〜13歳までは基礎指導年齢 |
4 |
5 |
6 |
| 3、14〜17歳は性被害の指導年齢 |
7 |
8 |
9 |
| 4、18歳以上は成人の防犯指導 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
講師料金一覧表
| |
1〜2時間前後 |
半日(4時間前後) |
1日(8時間前後) |
| NPO・ボランティア・公的団体・機関など |
5〜8万円(応相談) |
(応相談) |
(応相談) |
| 一般企業・商業団体など |
10〜15万円(応相談) |
(応相談) |
(応相談) |
|
上記料金は目安です。料金についてはご相談ください。(交通費は別途実費要) |
|
講演およびセミナー他・活動の一例
川越市北図書館、海老名市自治会連合会、豊田市防災防犯課、豊田氏上郷支所、町田市防犯課、
静岡県自治会連合会、前橋市教職員夏期講習会、多摩市子ども見守りシンポジューム、荒川区障害者
センター、千代田区高齢者大学、世界文化社60周年記念全国講演、千葉県稲毛マンション管理組合、
東大阪市保育園、横浜市立岡村小学校、三重県生活部、藤枝市市民グループ、熊本市学校法人、熊谷市
市民課、栃木県教育委員会、江南市青年会議所、泉佐野市私立保育会、富山県知事室、富山県防犯協会、
富山県教育委員会、富山県PTA連合会、富山県魚沼市、砺波市、富山市、黒部市、高岡市、氷見市、滑川市、
下新川町、栃木県烏山教育委員会、川口市南平PTA連絡協議会、国分寺市防犯課、関西電力大阪本社、セキスイ
ハウス特建事業部、守谷市市民協動推進課、石川県教育委員会、大阪府警備業組合、セントラル警備保障、
岐阜県安全対策事業私立幼稚園連合会、豊田市高橋支所、群馬県教育委員会、豊田市松平支所、渋谷区危機管理課、
綾部市市民大会、長浜市市民大会、世田谷区危機管理課、栃木県暮らしの安全課、千葉県野田市、横浜市教育
支援協会「浜っこクラブ」、川越市東部地域ふれあいセンター、守谷市市民大学、柏市役所、海老名市文化会館、
調布市文化会館たづくり、阿佐ヶ谷地域区民センターなど他多数。
平成28年(2016年)度
講演・セミナー・マスコミ出演など
1月21〜22日 1月度/防犯診断士資格取得セミナー
2月18〜19日 2月度/防犯診断士資格取得セミナー
|
|
| 通り魔事件が多発する社会の到来 |
7月5日、大阪で「仕事もなく、借金だらけで、生きているのが嫌になった」「誰が死んでもかまわない」「刃物では人をたくさん殺せないから。ガソリンを使おう」 などと考えて、近くのパチンコ店内にガソリンを巻いて火をつけ4人を殺害し、18名に重傷を負わせた41歳の男が警察に」出頭した。 昨年3月の「荒川沖駅事件」、同年5月の「秋葉原事件」 、11月の「駅ビル書店2女性刺殺事件」など、理不尽な殺人事件が多発している。
これらの事件は、理由なき殺人と称されるが、犯人にはちゃんとした理由がある。殺される人々に、殺されなければならない理由
がないから「理由なき殺人」となるのだ。これらの犯罪は防ぎようがないとされている。だが、犯人には明確な理由があり、さらに、
犯行をイメージし、計画し、準備し、時ととして中止したり延期したりしているのである。そのような彼らの犯行を避ける方法がないわけがない。その最も重要なのが、犯行後「人格障害」とされる彼らを育てた「保護者」の存在である。だが、保護者にだけ責任を求めるのは不条理である。何故なら、保護者に対する「子育ての啓発や啓蒙」がまったく行なわれていないからだ。これらかも「理由なき殺人」といわれる事件が多発する。そして、ガソリンなどを使った、新たな、防ぐのが難しい手口による「大量殺人」が発生することになる。防ぐことができる可能性が高いケースが多いのだから、ぜひ真剣に考えてみてほしいものだ。
|
| 守谷市主催 「市民のための防犯講座」 2日目 第2部 「こどもの防犯の基礎知識」 |
日時 平成21年6月14日 11時00分〜12時00分
場所 守谷市中央公民館
主催 守谷市
内容 ・1日目/2講座「防犯の基礎」「地域防犯の基礎」
・2日目/2講座「子どもの防犯の基礎」「施設防犯の基礎」
・3日目/2講座「身辺防犯の基礎」「経済防犯の基礎」
■子どもの防犯 基本編
・子どもの防犯とは
・子どもはなぜ簡単に被害者になってしまうのか
・子どもは誰が守るのか、守れるのか
・守るものはなにか
・子どもは誰に、どこで、どのようなダメージや被害をうけているのか
・8歳の子どもと11歳の子どもの子どもの守り方が同じで本当にいいのか
・子どもの防犯の基本1/保護者だけでは守れない
・子どもの防犯の基本2/年齢別防犯と性別指導
・子どもの防犯の基本3/12のテーマ
・4〜8歳の防犯は「保護防犯」と「心の防犯」
・9〜13歳は「基礎指導年齢」「子どもの自力防犯指導」
・14〜17歳は「性別指導」「非行抑止指導」
・18歳以上は「自立指導」
・あなたが知りたいのはどの年代の子どもの防犯なのか
・それは女児、女子、女性か
・男児、男子、男性なのか
・子どもの守り方は、スポーツの競技と同じぐらい多様である。
子どもたちを守る責務は保護者にある。保護責任、指導責任、結果責任の三つだ。だが、保護者だけでは子どもたちは守れない。街や地域の、あるいは国や社会の手助けがなければ守れないのだ。多くの権力者が、「子どもたちを街や地域の、社会や国の、大きく言えば人類の財産であり宝であると思っていない。お金が、道路が、会館が財産であり宝であるなどと思っている。そのようなものにだけお金をかけようとするのをみればわかる。 政策が貧困だから、保護者は、子どもを、家族を愛し、隣人を敬い、街や地域を担う、社会に役立つ人材に育てられないでいる。今、多くの子どもたちの心が傷つき、壊れ、欠け、病もうとしている。 守らねばならない。守る責務が私たち大人にあるからだ。 |
| マンションなどの集合住宅の防犯コンサルティング |
3月30日、千葉市にある集合住宅(約450世帯、分譲マンション築20年)の防犯診断および安全性確保のための設計をさせていただいた。打ち合わせから調査、設計まで約4ヶ月間におよぶコンサルティング活動だった。このマンションに住む住人(特に子どもや女性)は幸せである。恵まれていると思う。何故なら、管理組合の役員の皆様が「安全で安心して暮らせるマンションにする」ために、貴重な時間を費やして防犯構築に不可欠な知識を学習しノウハウを学ぶことから始められた。その姿勢や精神は尊さすら感じるほどであった。たしかに「安全なマンション」になれば付加価値が高くなることは間違いない。しかし、それだけの動機では長くは続かない。
前述の例でも明らかなように、集合マンションには危ない箇所や死角・盲点となる場所がたくさん存在する建物である。そのリスク箇所を徹底的に抽出し対策を施せば安全性は相当高くなる。これほど素晴らしい役員の方々がおられるマンションの住人は幸せであるというのはそういう意味である。
|
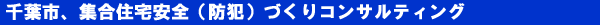 |
日 時 平成17年12月中旬〜平成18年3月末日
場 所 千葉市内
依頼主 当該マンション管理組合(約450世帯)
概 要
■防犯診断調査結果報告書
共同住宅および団地などに共通する防犯の要点
◇犯罪動向、犯罪形態、被害状況などの概要(侵入犯罪者の動機と目的の4段階、4つの手口)
当該団地住宅および団地の地域特性上の防犯の要点
◇当該地域における犯罪動向、犯罪形態、被害状況などの概要/所轄警察署および交番の現調/犯罪発生件数の推移状況と主要罪種対策など、ほか
■リスクの抽出報告書
当該共同住宅および団地の構造上のリスクの抽出
◇近接行為、侵入行為、実行行為、逃走行為に関するポイント
◇ゾーンデフェンス/第一ゾーン(敷地境界線)/第二ゾーン(敷地内防御)/第三ゾーン(建物外周(境界)防御/第四ゾーン(建物内防御)/第五ゾーン(室内境界線防御)/第六ゾーン(室内防御)ほか
■リスク対策概算書
当該共同住宅および団地の危険箇所と具体的対策
◇判断基準と評価および対策近接行為/第一ゾーン(敷地境界線)/第二ゾーン(敷地内防御)/第三ゾーン(建物外周(境界)防御/第四ゾーン(建物内防御)/第五ゾーン(室内境界線防御)/第六ゾーン(室内防御)ほか
■総合調査報告書
具体的対策に要する費用見積もり
◇危険対策および優先順位/第一ゾーン(敷地境界線)/第二ゾーン(敷地内防御)/第三ゾーン(建物外周(境界)防御/第四ゾーン(建物内防御)/第五ゾーン(室内境界線防御)/第六ゾーン(室内防御)ほか
マンションには危ない箇所がたくさん存在する。特に子どもたちや女性が性的被害を受けるケース
が少なくない。だが、深刻な性被害であればあるほど親や家族が風評被害などの二次被害やダメー
ジなどから守るために泣き寝入りをしてしまう事例が多発している。
平成12年、宮城県でマンションの敷地内などで遊んでいた女児約100名にレイプなどの凶悪な性犯
罪を行なった男がいた。届けられたのはわずか3件である。なぜ、このように多くの被害が発生した
のか、それは簡単に犯行が行なえるからにほかならない。マンションの安全度を強化するのはそこに
住む大人の責任である。
|
こどもたちを犯罪被害者にしないために、
子どもを非行や犯罪者にしないために
親子がともに幸せになるために
保護者のための
子どもの育て方と守り方の要点
|
世界第2位の経済大国になった平成以後の特徴として、家族の絆の崩壊現象が顕著になっている。
些細な出来事で挫折しやすい子どもたちが増えている。
犯罪被害にあいやすく育てられる子どもが増えている。
逆に非行や犯罪行為に走りやすく育てられる子どもたち増えている。
我が子を殺人者にし、家族を被害者にしてしまうような子育てをする保護者が増えている。
誤った子育ては、子どもだけでなく家族を巻き込んで不幸と禍をもたらすことを知らない保護者が増えている。
家族を傷つける事件、不登校、引きこもり、ニート、家庭内暴力などの事件が報道されても、
家には関係ない、うちの子には関係ないと思っている保護者は少なくない。
これらの事件が、いつでも、どの家庭でも、どの子どもにも発生する可能性があることを知らないのである。
さらに、保護者がわが身を削り、心を砕き、莫大な時間と労力と心血を注いで大切に育てた、かけがえのない我が子を
一瞬にして破壊し人生を破滅させる犯罪被害から守ることを放置している保護者も少なくない。
かけがえのない我が子を健やかに育ててほしい、守ってほしい。
子どもは保護者や家族の宝であると同時に街や地域の、国や世界の、人類の宝なのだから。
科学が進歩した今日、健やかなこどもの育て方の基本は確立している。
子どもを犯罪被害者にしないための知識も確立している。
一人でも多くの保護者に知ってほしいものである。
|
街や地域の子どもたちを守り育むために
特別講座 親子がともに幸せになる
子育てと子どもの守り方・保護者編
|
内 容
■第一話 子育て基本 5つの要点 (親子がともに幸せになる子育てには基本がある)
◇真の子育てとは (基本をしらなければ正しく育てられない・ほか)
◇保護者がすべてを決める (親という漢字が示す親の姿勢・ほか)
◇子育ての黄金律 (現代科学が証明した優れた子育ての道しるべ・ほか)
◇子育ての5段階 (年齢・時期別に必須のテーマがある・ほか)
◇子育ての5つのテーマ (保護者が誤りやすい最初の扉・ほか)
健常に生まれた子どもに備わっている脳機能に大差はない。
すべての子どもに無限の可能性と未来がある。
精神や魂の強さ、正しさ、清清しさ、しなやかさなどすべてが同等に備わっている。
要は、保護者、両親、母親の育てかたできまる。
■第二話 子育ての要点1 0〜6歳期 (不幸と禍をもたらす誤った子育てしないために)
◇豊かな心を育む要点 (現代科学が証明した方法がある/ほか)
◇可能性を無限に開く、脳の育て方 (これが早期教育、英才教育、幼児教育の極意)
◇不可欠な躾の指導と要点 (躾と子育ての違いを知っていますか/ほか)
◇能力は個性であり、3つ以上ある (子どもは天才、伸ばすのは親しだい/ほか)
子育てに不可欠なテーマがある。
子育てには、1度の食事では生きていけないように、毎日、数時間おきに必要なものがある。
逆に、行なってはいけないこもある。
深刻な害をもたらす、インフルエンザのようなものがある。
これを知らなければ適切な子育てができない。
■第三話 子育ての要点2 7〜15歳
◇誤った子育ての深刻なリスク (子どもの心や能力はは叱られて育たない、ほか
◇子育てアセスメント (乳幼児期に不足していたものがあれば補わなければならない、他)
◇学習能力向上の極意 (親は勉強を教えてはいけない、ほか)
子どもの能力を、学習能力(成績や試験結果)向上だけに偏る子育てをしてはいけない。
さらに暴力や叱咤をともなう家庭内学習は修復できないほどの傷を子どもにもたらすことになる。
それが親子の絆が壊れる最大の原因。
現代は、そのようなケースが多すぎる。
■第四話 子どもの防犯の基本、5つの要点 (子どもの命と体と心を守る基本)
◇防犯とはなにか (基本を知らなければ守れない、ほか)
◇子どもはなぜ、犯罪被害を受けるのか
◇子どもの防犯の基本 (子どもの防犯は4段階、ほか)
◇子どもの防犯12のテーマ (子どもの防犯は年齢別、性別、関係者別が基本、ほか)
◇守るものは何か、誰が守れるのか (守るものは命と体と心、ほか)
心血を注いで守り育んできた愛する我が子を、一瞬で挫折させ、不幸にする出来事がある。
それが、犯罪被害である。
このような忌まわしい犯罪から最愛の我が子を守らなければならない。
守るための知識を備えなければならない。
■第五話 子どもの防犯の要点 (愛する我が子を不幸にする犯罪から守るために)
◇0〜3歳は心の防犯 (保護者でなければ守れない、ほか
◇4〜8歳は保護防犯 (保護者だけでは守れない、他)
◇9〜13歳は基礎指導 (大人だけでは守れない、ほか)
◇9〜17歳は性別指導 (男女でうける被害が違う、ほか
◇18歳以上は自立指導 (一人暮らしで発生する深刻な犯罪被害リスク、ほか)
適切な防犯とは科学的でなければならない。
子どもの防犯では曖昧な指導が命取りになることがある。
子どもには子どもの守り方がある。
それが防犯知識を盾として守るということだ。
防犯の基本とは自分で守ることなのである。
|
|
|